スタッフブログ
2025.05.21
『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』
こんにちは!
今回のスタッフブログはスイミングの荒井です。
新年度がはじまり、もう夏の足音が聞こえてくるようになりましたね。
プールに来る子どもたちも「暑い、暑い」と言いながら入っていることが増えてきました。
さて、今回私が読んだ本は、今井むつみさんの『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』です。
今回のスタッフブログはスイミングの荒井です。
新年度がはじまり、もう夏の足音が聞こえてくるようになりましたね。
プールに来る子どもたちも「暑い、暑い」と言いながら入っていることが増えてきました。
さて、今回私が読んだ本は、今井むつみさんの『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』です。
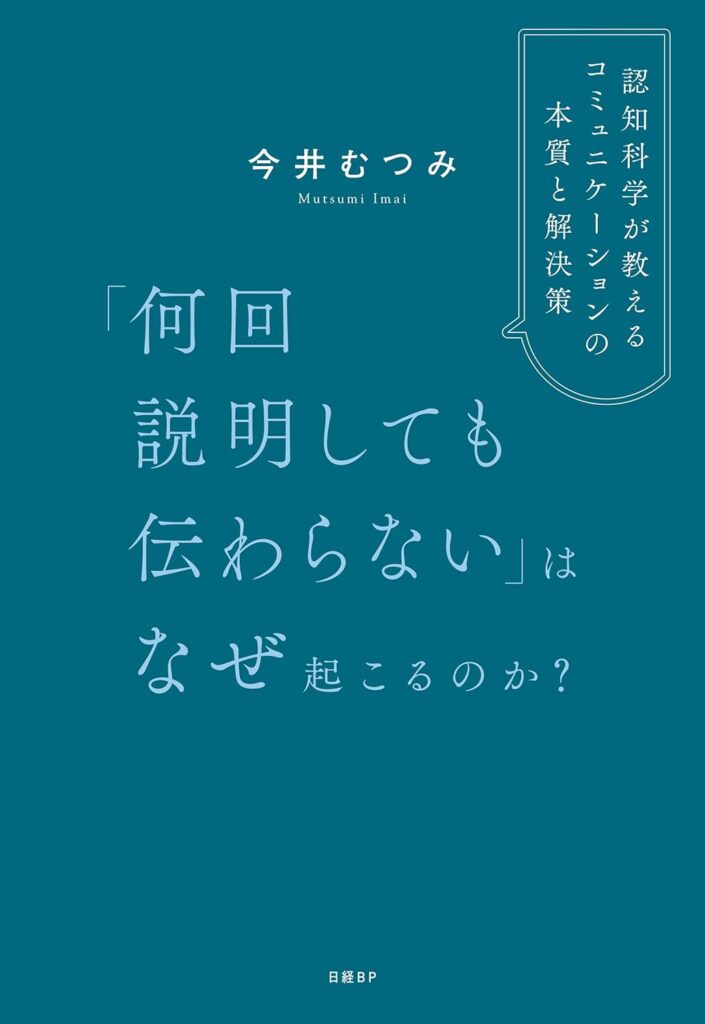
人に教えるといった場面の違和感の一つに、「何度教えても伝わらない」「説明しているはずなのに、子どもが理解できていない」ということがあると思う。
教える側も、全力で説明し、工夫して教えている。それにもかかわらず、思うように伝わらず、成果に結びつかない。その原因を“理解力の差”や“意欲の欠如”に求めてしまいがちだが、本書『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』は、そうした表面的な問題ではなく、言葉の意味が人によって違う”という前提に解説している。
●言葉は単なるラベルではなく、経験を通して構築される概念の表現である
この言葉だけ聞くとたいへん難しいように感じるが、私が読み進めていく上で感じたこと、理解していった内容を掻い摘んで書いていきます。
たとえば「分数」や「読解力」あるいは「リーダーシップ」といった言葉を教えるとき、教える側と子ども側でその言葉が指し示す意味の構造が異なっていれば、どれだけ丁寧に説明しても、子どもは理解しようがない。教師が使っている「分かる」という言葉と、子どもが感じている「分かった」は、別の次元にあることさえある。そこに気づけないと、「説明したのに理解していない」と感じ、無力感に陥ってしまうのだという。
今井氏は、「概念は個人の経験と環境によって形作られる」と繰り返し説明している。教室に集まる子どもたちは、皆違った背景を持ち、異なる生活体験を通じて言葉を学んできている。そのため、同じ言葉を使っていても、その理解の深さや意味の捉え方にはばらつきがある。これは「理解の個別性」とも言える現象であり、様々な教育現場において起こりうる現象である。
さらに本書は、「言葉の意味を共有するには、時間と対話が必要だ」という重要な事実を教えてくれる。教える側がどれほど明確に説明したと思っても、それを聞いた子どもが本当に理解するには、自分の言葉で言い直したり、他の事例に応用してみたり、試行錯誤を通じて自分なりの「意味の構造」を築く時間が必要なのだ。
この本でよく登場する言葉として、「アナロジー(類推)」というものがある。言葉自体が難しいため、簡単に説明をすると「新しいものを伝える際に違うものに例える」といったことである。
新しい概念を理解するためには、子どもたちが既に持っている知識と結びつける“橋”が必要である。たとえば、数学の「比」を教えるときに、料理のレシピを使って説明することで、「この2つの材料の比は3:1だよ」というように、具体的な文脈と関連づける。また、ゲームでいうとこういうことだよなどである。これは子どもにとって新しい知識を自分の世界と接続する手がかりとなり、理解が深まる。この本ではこのような例を通じて、「説明とは翻訳であり、橋渡しである」と述べている。
●「人は意味を共有することで初めて本当に理解し合える」
これは教育現場における「対話」の重要性を再確認させてくれる。教師が一方的に話し続ける授業ではなく、子どもが自分の考えを表現し、それに対して教師や仲間がフィードバックを返すような、インタラクティブな学びこそが、本当の「伝わる授業」を可能にする。
そして、子どもが「わかっていない」ときに、それを“失敗”や“能力の不足”と捉えるのではなく、「まだ概念の土台が築かれていない状態」と理解する姿勢も、教育者にとって重要な視点転換だ。これは、子どもに対する信頼にもつながる。「わからない」は悪いことではなく、学びのスタート地点である。この認識が教室に根付けば、子どもたちはより安心して学び、試行錯誤し、理解を深めていくことができるだろう。
●「教えることの意味の再定義」
今回私が読んで頂いた方に最も伝えたいと思ったのがこの内容でした。
ご家庭で、保護者が子どもに「ちゃんと説明したのに、なぜわからないの?」と感じる場面は多いのではないでしょうか。しかしそれは、親が当たり前だと思っている知識や常識が、子どもにとっては未知のものであるからかもしれない。意味を共有するには、丁寧な対話と背景の説明が必要であり、決して“言い聞かせる”ことでは解決しない。意味は相手と「一緒につくる」ものである。だからこそ、家庭においても、子どもの言葉や理解を尊重し、そこからスタートするコミュニケーションが求められるといった内容です。
最も私はまだ子どもがおりませんので、想像の中での話にはなってしまうのですが…。
この本は難解な言葉こそ出てきますが、そこまで難しい内容ではありません。具体例やわかりやすい説明によって、「なぜ伝わらないのか」という疑問に答えてくれる。そして、「伝える」とは何か、「わかる」とはどういうことかという、「教える」というほぼすべての人がするであろう行為のスタートラインとなるような本でした。
教えるということの中でやはり一番大変なのが「わかってもらうこと」だと思います。「わかってもらえない」と感じた時には「なぜ」ではなく「どうしたら」と考えて行動すべきだと改めてこの本を読んで感じることができました。疑問に思った時にはこのスタートラインに立てるようにこの本を紹介させていただきました。わかってもらえないと感じた時には「自分がまだ相手への橋を架けられていないのだ」と感じられるような自分になっていきたいと思います。
教える側も、全力で説明し、工夫して教えている。それにもかかわらず、思うように伝わらず、成果に結びつかない。その原因を“理解力の差”や“意欲の欠如”に求めてしまいがちだが、本書『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』は、そうした表面的な問題ではなく、言葉の意味が人によって違う”という前提に解説している。
●言葉は単なるラベルではなく、経験を通して構築される概念の表現である
この言葉だけ聞くとたいへん難しいように感じるが、私が読み進めていく上で感じたこと、理解していった内容を掻い摘んで書いていきます。
たとえば「分数」や「読解力」あるいは「リーダーシップ」といった言葉を教えるとき、教える側と子ども側でその言葉が指し示す意味の構造が異なっていれば、どれだけ丁寧に説明しても、子どもは理解しようがない。教師が使っている「分かる」という言葉と、子どもが感じている「分かった」は、別の次元にあることさえある。そこに気づけないと、「説明したのに理解していない」と感じ、無力感に陥ってしまうのだという。
今井氏は、「概念は個人の経験と環境によって形作られる」と繰り返し説明している。教室に集まる子どもたちは、皆違った背景を持ち、異なる生活体験を通じて言葉を学んできている。そのため、同じ言葉を使っていても、その理解の深さや意味の捉え方にはばらつきがある。これは「理解の個別性」とも言える現象であり、様々な教育現場において起こりうる現象である。
さらに本書は、「言葉の意味を共有するには、時間と対話が必要だ」という重要な事実を教えてくれる。教える側がどれほど明確に説明したと思っても、それを聞いた子どもが本当に理解するには、自分の言葉で言い直したり、他の事例に応用してみたり、試行錯誤を通じて自分なりの「意味の構造」を築く時間が必要なのだ。
この本でよく登場する言葉として、「アナロジー(類推)」というものがある。言葉自体が難しいため、簡単に説明をすると「新しいものを伝える際に違うものに例える」といったことである。
新しい概念を理解するためには、子どもたちが既に持っている知識と結びつける“橋”が必要である。たとえば、数学の「比」を教えるときに、料理のレシピを使って説明することで、「この2つの材料の比は3:1だよ」というように、具体的な文脈と関連づける。また、ゲームでいうとこういうことだよなどである。これは子どもにとって新しい知識を自分の世界と接続する手がかりとなり、理解が深まる。この本ではこのような例を通じて、「説明とは翻訳であり、橋渡しである」と述べている。
●「人は意味を共有することで初めて本当に理解し合える」
これは教育現場における「対話」の重要性を再確認させてくれる。教師が一方的に話し続ける授業ではなく、子どもが自分の考えを表現し、それに対して教師や仲間がフィードバックを返すような、インタラクティブな学びこそが、本当の「伝わる授業」を可能にする。
そして、子どもが「わかっていない」ときに、それを“失敗”や“能力の不足”と捉えるのではなく、「まだ概念の土台が築かれていない状態」と理解する姿勢も、教育者にとって重要な視点転換だ。これは、子どもに対する信頼にもつながる。「わからない」は悪いことではなく、学びのスタート地点である。この認識が教室に根付けば、子どもたちはより安心して学び、試行錯誤し、理解を深めていくことができるだろう。
●「教えることの意味の再定義」
今回私が読んで頂いた方に最も伝えたいと思ったのがこの内容でした。
ご家庭で、保護者が子どもに「ちゃんと説明したのに、なぜわからないの?」と感じる場面は多いのではないでしょうか。しかしそれは、親が当たり前だと思っている知識や常識が、子どもにとっては未知のものであるからかもしれない。意味を共有するには、丁寧な対話と背景の説明が必要であり、決して“言い聞かせる”ことでは解決しない。意味は相手と「一緒につくる」ものである。だからこそ、家庭においても、子どもの言葉や理解を尊重し、そこからスタートするコミュニケーションが求められるといった内容です。
最も私はまだ子どもがおりませんので、想像の中での話にはなってしまうのですが…。
この本は難解な言葉こそ出てきますが、そこまで難しい内容ではありません。具体例やわかりやすい説明によって、「なぜ伝わらないのか」という疑問に答えてくれる。そして、「伝える」とは何か、「わかる」とはどういうことかという、「教える」というほぼすべての人がするであろう行為のスタートラインとなるような本でした。
教えるということの中でやはり一番大変なのが「わかってもらうこと」だと思います。「わかってもらえない」と感じた時には「なぜ」ではなく「どうしたら」と考えて行動すべきだと改めてこの本を読んで感じることができました。疑問に思った時にはこのスタートラインに立てるようにこの本を紹介させていただきました。わかってもらえないと感じた時には「自分がまだ相手への橋を架けられていないのだ」と感じられるような自分になっていきたいと思います。
2025.12.28
『とりあえずやってみる技術』
2025.12.26
『ながーい5ふん みじかい5ふん』
2025.12.09
『Little Book of Choice Theory …
2025.12.02
『夢2.0 ~夢を再定義する~』
2024.12.31
『勝つ理由。<3人の金メダリストを育てた名将がひもとく勝利の…
2024.12.31
『このプリン、いま食べるか? ガマンするか? 一生役立つ時間…
2024.12.05
『ディズニー そうじの神様が教えてくれたこと』
2024.11.30
『ゆっくり変わる』
2023.12.30
子育てに必要な4つのこと
2023.12.01
『習慣が10割』
2023.12.01
『リーダーは話し方が9割』
2023.11.01
『選択の科学 コロンビア大学ビジネススクール特別講義』
2021.10.16
『運動の大切さ』
2021.10.16
『伸びる子どもは◯◯がすごい』
2021.10.01
「どうせ無理」と思っている君へ
2021.10.01
『本当の「頭のよさ」ってなんだろう?』
横浜本校

みなとみらい校

江古田校

金沢八景校

横浜本校(スイミング)








