スタッフブログ
2025.09.01
『心をつかみ人を動かす説明の技術』
こんにちは原コーチです。
まだまだ暑い日が続きますが体調に気をつけて元気にプールで泳ぎましょう!
今回読んだ本は「心をつかみ人を動かす説明の技術」です
私は水泳指導に携わる中で常に感じてきた課題があります。
それは、「どうすればもっとわかりやすく、伝わる指導ができるのか」ということです。
こちらは丁寧に説明しているつもりでも、子どもたちにうまく伝わっていないなと感じる時がありました。
まだまだ暑い日が続きますが体調に気をつけて元気にプールで泳ぎましょう!
今回読んだ本は「心をつかみ人を動かす説明の技術」です
私は水泳指導に携わる中で常に感じてきた課題があります。
それは、「どうすればもっとわかりやすく、伝わる指導ができるのか」ということです。
こちらは丁寧に説明しているつもりでも、子どもたちにうまく伝わっていないなと感じる時がありました。
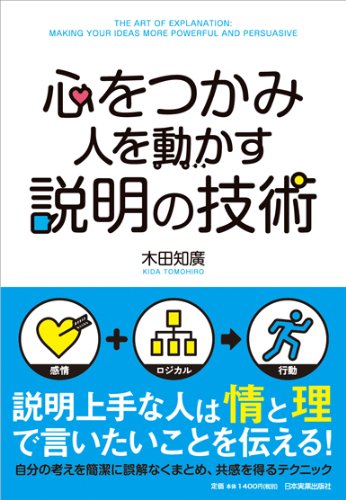
そんなとき、「説明の仕方そのものに原因があるのではないか」と感じていた中で出会ったのがこの本です。
この本には、指導者としてだけでなく、ひとりの「伝える立場」にある人間として多くの気づきが詰まっていました。
まず、この本の中で最も強く印象に残ったのは、「説明とは、相手の頭の中に“納得”を生み出すこと」という考え方です。
これまで私は、情報を正しく伝えること、つまり「教えること」に重点を置いていました。
しかし、説明とは「相手が理解して、行動を起こす状態に導くこと」だと言っていて、まさに水泳の指導でも同じことが言えるのではないかと思いました。
こちらがいくら正しいフォームや理論を伝えても、相手が納得できていなければ、その技術は身につきません。相手の心に届き、行動が変わって初めて、説明は成功したと言えます。
この考え方を知ったとき、私はこれまでの自分の指導を振り返ってみました。
何度同じことを伝えても直らないなと感じた時、「なぜ分かってくれないのか」と思ってしまっていた自分が恥ずかしくなりました。
説明が伝わらないのは、相手の理解力のせいではなく、自分の説明の仕方に問題があるのかもしれない、と思う様に見直すきっかけとなりました。
次に心に残ったのが、「説明には型がある」という点です。
「結論→理由→具体例→再結論」の型は、水泳指導にもすぐに応用できると感じました。
例えば、ある子どもに「もっと腕を遠くに伸ばして泳ごう」と伝えたいとした時に、ただ「腕を伸ばして」と言うだけでは、なぜそうするべきなのか分からなので、「腕はなるべく遠くに伸ばして入水しよう(結論)。なぜなら、遠くで水をキャッチすることで進む力が増えるからだよ(理由)。例えば、肩の真下で手を入れている子は進みが遅くなりやすいけど、前に伸ばしている子はスーッと前に進むよね(具体例)。だから、できるだけ腕を前に伸ばして泳いでみよう(再結論)」というように、筋道を立てて説明することで、納得しやすくなるはずです。
また、説明する際には「聞き手の準備」ができているかを見極めることも大切だと書いていました。
これは水泳の現場では特に重要だと感じます。
子どもたちは常に集中しているとは限らず、疲れていたり、水の中で遊びたい気持ちが強かったりします。その状態でいくら理屈を丁寧に話しても、頭に入らないのは当然です。だからこそ、指導前にしっかりと目を合わせ、声をかけ、関心を引きつける工夫が必要になります。
私自身、つい説明を急いでしまいがちでしたが、これからは「話す前の準備」にももっと意識を向けようと思いました。
さらに、「言葉を減らす勇気」もまた重要なポイントだと感じました。説明というと、どうしてもたくさんの情報を詰め込もうとしてしまいます。
しかし、本当に伝わる説明というのは、シンプルで的確なものであるべきです。
泳ぎのポイントも、一度にすべて伝えるのではなく、今日は「キック」、次は「ストローク」というように、焦点を絞って説明することで、子どもたちの集中力や理解度も格段に上がると思います。
ただ教えるのではなく、相手の心に届くように伝えること。そのためには、言葉の選び方、順序、タイミング、そして相手への思いやりが必要だということを学びました。水泳というスポーツは、技術の積み重ねであり、指導者の言葉ひとつで子どもの成長スピードは大きく変わります。
だからこそ、「説明の技術」は水泳指導者にとって最も重要なスキルの一つだと再認識しました。
今後は、ただの「説明」ではなく、「納得を生み、行動を変える説明」を意識しながら、一人ひとりの理解に寄り添った指導を心がけ、水泳指導を通じて子どもたちの心を動かすことができるよう、私自身の伝え方を磨き続けていきたいと思います。
この本には、指導者としてだけでなく、ひとりの「伝える立場」にある人間として多くの気づきが詰まっていました。
まず、この本の中で最も強く印象に残ったのは、「説明とは、相手の頭の中に“納得”を生み出すこと」という考え方です。
これまで私は、情報を正しく伝えること、つまり「教えること」に重点を置いていました。
しかし、説明とは「相手が理解して、行動を起こす状態に導くこと」だと言っていて、まさに水泳の指導でも同じことが言えるのではないかと思いました。
こちらがいくら正しいフォームや理論を伝えても、相手が納得できていなければ、その技術は身につきません。相手の心に届き、行動が変わって初めて、説明は成功したと言えます。
この考え方を知ったとき、私はこれまでの自分の指導を振り返ってみました。
何度同じことを伝えても直らないなと感じた時、「なぜ分かってくれないのか」と思ってしまっていた自分が恥ずかしくなりました。
説明が伝わらないのは、相手の理解力のせいではなく、自分の説明の仕方に問題があるのかもしれない、と思う様に見直すきっかけとなりました。
次に心に残ったのが、「説明には型がある」という点です。
「結論→理由→具体例→再結論」の型は、水泳指導にもすぐに応用できると感じました。
例えば、ある子どもに「もっと腕を遠くに伸ばして泳ごう」と伝えたいとした時に、ただ「腕を伸ばして」と言うだけでは、なぜそうするべきなのか分からなので、「腕はなるべく遠くに伸ばして入水しよう(結論)。なぜなら、遠くで水をキャッチすることで進む力が増えるからだよ(理由)。例えば、肩の真下で手を入れている子は進みが遅くなりやすいけど、前に伸ばしている子はスーッと前に進むよね(具体例)。だから、できるだけ腕を前に伸ばして泳いでみよう(再結論)」というように、筋道を立てて説明することで、納得しやすくなるはずです。
また、説明する際には「聞き手の準備」ができているかを見極めることも大切だと書いていました。
これは水泳の現場では特に重要だと感じます。
子どもたちは常に集中しているとは限らず、疲れていたり、水の中で遊びたい気持ちが強かったりします。その状態でいくら理屈を丁寧に話しても、頭に入らないのは当然です。だからこそ、指導前にしっかりと目を合わせ、声をかけ、関心を引きつける工夫が必要になります。
私自身、つい説明を急いでしまいがちでしたが、これからは「話す前の準備」にももっと意識を向けようと思いました。
さらに、「言葉を減らす勇気」もまた重要なポイントだと感じました。説明というと、どうしてもたくさんの情報を詰め込もうとしてしまいます。
しかし、本当に伝わる説明というのは、シンプルで的確なものであるべきです。
泳ぎのポイントも、一度にすべて伝えるのではなく、今日は「キック」、次は「ストローク」というように、焦点を絞って説明することで、子どもたちの集中力や理解度も格段に上がると思います。
ただ教えるのではなく、相手の心に届くように伝えること。そのためには、言葉の選び方、順序、タイミング、そして相手への思いやりが必要だということを学びました。水泳というスポーツは、技術の積み重ねであり、指導者の言葉ひとつで子どもの成長スピードは大きく変わります。
だからこそ、「説明の技術」は水泳指導者にとって最も重要なスキルの一つだと再認識しました。
今後は、ただの「説明」ではなく、「納得を生み、行動を変える説明」を意識しながら、一人ひとりの理解に寄り添った指導を心がけ、水泳指導を通じて子どもたちの心を動かすことができるよう、私自身の伝え方を磨き続けていきたいと思います。
2025.12.28
『とりあえずやってみる技術』
2025.12.26
『ながーい5ふん みじかい5ふん』
2025.12.09
『Little Book of Choice Theory …
2025.12.02
『夢2.0 ~夢を再定義する~』
2024.12.31
『勝つ理由。<3人の金メダリストを育てた名将がひもとく勝利の…
2024.12.31
『このプリン、いま食べるか? ガマンするか? 一生役立つ時間…
2024.12.05
『ディズニー そうじの神様が教えてくれたこと』
2024.11.30
『ゆっくり変わる』
2023.12.30
子育てに必要な4つのこと
2023.12.01
『習慣が10割』
2023.12.01
『リーダーは話し方が9割』
2023.11.01
『選択の科学 コロンビア大学ビジネススクール特別講義』
2021.10.16
『運動の大切さ』
2021.10.16
『伸びる子どもは◯◯がすごい』
2021.10.01
「どうせ無理」と思っている君へ
2021.10.01
『本当の「頭のよさ」ってなんだろう?』
横浜本校

みなとみらい校

江古田校

金沢八景校

横浜本校(スイミング)








