スタッフブログ
2025.11.01
『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた 「なぜ」と聞かない質問術』
みなさん、こんにちは。
今年の夏は長くて、いつ秋が来るのか?と思っていたら、急に寒くなりましたね。インフルエンザなども流行ってきているようなので、風邪を引かないように気を付けたいですね。
さて、今回読んだ本は、私が前からこんな本ないかなーと探していた本です。
ありがたいことに相談を受けることが、多々あります。相談内容を聞いて私なりの考えを伝えますが、それが本当に相手の欲しかった答えなのか、悩みは本当に解決したのか、相手の表情を見ていて、このように感じることがあります。また、私から相手へ質問をした際に、思っていた回答が得られないことも多くあります。これは、話し方ではなく、質問の内容を変えないといけないのかなと考えるようになりました。
話し方についての著書は多く見かけますが、「質問」についての著書がなかなか見つからなかったので、本屋さんでこの本を見つけたときにはガッツポーズをしました。
その本のタイトルは、中田豊一さんの【「なぜ」と聞かない質問術】です。
今年の夏は長くて、いつ秋が来るのか?と思っていたら、急に寒くなりましたね。インフルエンザなども流行ってきているようなので、風邪を引かないように気を付けたいですね。
さて、今回読んだ本は、私が前からこんな本ないかなーと探していた本です。
ありがたいことに相談を受けることが、多々あります。相談内容を聞いて私なりの考えを伝えますが、それが本当に相手の欲しかった答えなのか、悩みは本当に解決したのか、相手の表情を見ていて、このように感じることがあります。また、私から相手へ質問をした際に、思っていた回答が得られないことも多くあります。これは、話し方ではなく、質問の内容を変えないといけないのかなと考えるようになりました。
話し方についての著書は多く見かけますが、「質問」についての著書がなかなか見つからなかったので、本屋さんでこの本を見つけたときにはガッツポーズをしました。
その本のタイトルは、中田豊一さんの【「なぜ」と聞かない質問術】です。
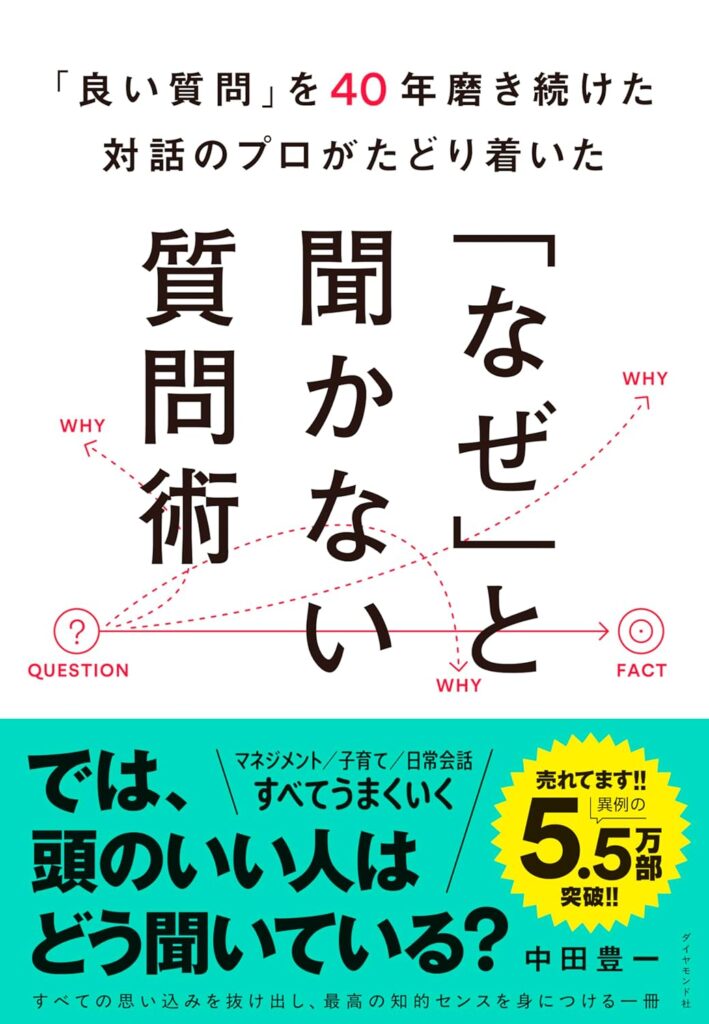
―「なぜ」と聞くと、意図せず相手の「思い込み」を引き出してしまうのです。―
この本は、これを知るところから始まります。
実際の会話内容や、質問術を使ってどのように変化するかなどもわかりやすく書かれていました。
ここからは、私が共感した部分や実践したいと感じた内容を抜粋していきます。
●「なぜ質問」は相手を問い詰める
「なぜ質問」を使ってしまうと、質問者は真の理由を突き止めたくて聞いているのに、回答者は思い込みや言い訳を言うという「会話のズレ」が起こります。
つまり、「なぜ」と聞いたときに出てくるのは、「理由」ではありません。第一に「その人が理由だと思い込んでいること」、第二に「理由に見せかけた、自己防衛するための言い訳」なのです。
そして、これに気づかずに話を進めてしまったときに発生するのが、「会話のねじれ」です。この聞く側と聞かれる側の間に生じる「ねじれ」こそがコミュニケーション不全の正体です。―――――――――――
この部分を読んだときに、その通りだと感じました。私が、誰かに話をした時に「なぜ」と聞かれると問い詰められているような感覚になり苦し紛れに言い訳を言っていることがあるなと思うことが何度かあったことをこの部分を読んで思い出しました。
そして思い込みや言い訳が出てしまうのが、質問の仕方だということに驚きました。
●「どうでした?」は相手に負担を与える
質問はしているものの、なんとなく惰性でコミュニケーションをとろうとしているだけで、知りたいことが具体的に浮かんでいないのです。「どう質問」も、どうとでも答えられるだけに、相手を戸惑わせたり、確信のない答えを強要したりする可能性が高い、よくない質問です。
聞く側はつい、気軽に「どう」と聞いてしまうのですが、これに答えるのは意外に面倒です。聞く側の意図と、答える側の現実がかみ合わない質問なので。「どう?」と聞いたとたんにコミュニケーションのねじれが始まるわけです。
―――――――――――
この部分を読んだときに、聞く側と答える側のどちらも経験があるなーと思いました。そして、聞かれた際は、どんな答え方をしたらいいのか困ったのに、いざ自分が聞く側になったら、同じように聞いていることもあるなと、思い返しました。
●「なぜ」と聞きたくなったら「いつ?」と聞く
「なぜ、どうして」と聞きたくなったら、それを一度飲み込んで、「いつ」という事実質問に置き換えて質問すべし、というものです。
「なぜ質問」の場合、質問の対象となるのは、「意識を生きる」「宿敵を生きる」にすぎない。初対面の人と話すのが「苦手」など、行為や出来事や現象です。つまり、その背景や原因や動機を「なぜ」という質問によって聞き出そうとするものです。これは言いくるめや都合のいい解釈、根拠の乏しい思い込みを引き出す良くない質問でしたね。この時「なぜ質問」は禁句にしてはいけません。
質問対象とする行為や出来事が一度きりの場合は、「そこにいつ就職したの?」など、「それをしたのはいつか」「起こったのはいつか」というような、そのことが起こった日時を特定する「いつ質問」に変換します。
特に継続的な出来事や現象、あるいは繰り返し起こっていることについては、初めと終わりがありますから、「一番最初はいつ?」または「一番最近はいつ?」と聞きます。
「いつ?」と聞いた後は、「その前に?」「その前は?」と時系列で聞き続けるのが筋道です。「なぜ?」と聞くと考え始めてしまいますが、「いつ?」「その前は?」と聞き続けられたら、思い出そうとしますよね。このプロセスが、思い込みを排して、事実を確認していく行為となるわけです。
―――――――――――
この部分を読んだときに、自分が、「いつ」と聞かれていたら、事実しか頭に浮かばないなと思いました。使う場面はそれぞれだとは思いますが、思い込みを排除して、事実を知るうえで重要な言葉だと感じたのと同時に、シンプルで使いやすいので意識して使っていきたいです。
●「どう」と聞かずに「何」「いつ」「どこ」「誰」と聞く
「なぜ質問」の対象は行為や出来事や現象で、目的はその背景や原因や動機を知ることでした。「どう質問」は、「どう?」のひと言で考えなどを一気に聞いてしまおうという怠惰な質問です。聞かれたほうは「相手が何が知りたいのかはっきりわからない状態」のまま、何が思いついたことを答えようとします。二人の間には当然、モヤがかかります。
ここでの基本公式は、その出来事や現象を少しだけ分解して、何がいつ****どこで「誰に(誰と)起こったか、と聞くことです。
以下の「どう質問」は、どのように変えられますか。考えてみてください。
例)試合、どうだった?(野球の試合を終えた友人に対して)
相手との関係にもよりますが、こちらが聞きたいことは「試合の結果」と「友人のプレーの出来(活躍具合)」に絞り込めるはずです。
まず、試合の結果は秘密でも何でもないでしょうから、突然聞いてもいいでしょう。ただ唐突さを避けるために、「相手は〇〇チームでしたよね?」などと軽い確認の質問をまず行ってから、「で、結果は?」と聞くとより自然に話に入っていけます。
友人のプレーの出来についても同じです。「前の試合と同じように、サードを守ったの?」と聞いてから「何を打ったの?」「最後まで出たの?」などと聞き続ければ、相手は必ず「打撃はよかったんだけど、大事なところでエラーしてしまって...」などと自分から語り始めてくれるはずです。それをうけて、さらに聞いていけば、やがて相手から自発的に話をしてくれるという流れが自然にできていきます。そうなると、他の友人には話しにくいような微妙な話も出てくるかもしれません。
まどろっこしいように思えるかもしれませんが、このように、相手が答えやすい、事実質問から入っていくことで、状況を具体的に思い出してもらう環境を整えることができます。
正確に思い出して答えてもらえなければ、質問する意味がありません。
―――――――――――
この部分は、よく言ってしまうなーと率直に思いました。
教室での子どもたちに、「運動会はどうだった?」「今日はどうだった?」など、何気なく発してしまっていますが、このどう質問を置き換えると、「運動会は何組だったの?」「今日は朝何時に起きたの?」など、答えやすい質問にすることができるかなと思いました。
著書の中から私が共感した部分や実践したいと感じた内容を抜粋していきました。
思い込みではなく事実を思い出してもらう質問の方法や、答えやすい質問をすることで、相手が今どんなことを考えているのか、どんな気持ちなのかを知ることができると著書を通して知ることができました。
これらは著書の一部ですが、人と会話をする際には抜粋した部分を中心に思い出しながら、質問をしていきたいと思います。
有水愛佳
この本は、これを知るところから始まります。
実際の会話内容や、質問術を使ってどのように変化するかなどもわかりやすく書かれていました。
ここからは、私が共感した部分や実践したいと感じた内容を抜粋していきます。
●「なぜ質問」は相手を問い詰める
「なぜ質問」を使ってしまうと、質問者は真の理由を突き止めたくて聞いているのに、回答者は思い込みや言い訳を言うという「会話のズレ」が起こります。
つまり、「なぜ」と聞いたときに出てくるのは、「理由」ではありません。第一に「その人が理由だと思い込んでいること」、第二に「理由に見せかけた、自己防衛するための言い訳」なのです。
そして、これに気づかずに話を進めてしまったときに発生するのが、「会話のねじれ」です。この聞く側と聞かれる側の間に生じる「ねじれ」こそがコミュニケーション不全の正体です。―――――――――――
この部分を読んだときに、その通りだと感じました。私が、誰かに話をした時に「なぜ」と聞かれると問い詰められているような感覚になり苦し紛れに言い訳を言っていることがあるなと思うことが何度かあったことをこの部分を読んで思い出しました。
そして思い込みや言い訳が出てしまうのが、質問の仕方だということに驚きました。
●「どうでした?」は相手に負担を与える
質問はしているものの、なんとなく惰性でコミュニケーションをとろうとしているだけで、知りたいことが具体的に浮かんでいないのです。「どう質問」も、どうとでも答えられるだけに、相手を戸惑わせたり、確信のない答えを強要したりする可能性が高い、よくない質問です。
聞く側はつい、気軽に「どう」と聞いてしまうのですが、これに答えるのは意外に面倒です。聞く側の意図と、答える側の現実がかみ合わない質問なので。「どう?」と聞いたとたんにコミュニケーションのねじれが始まるわけです。
―――――――――――
この部分を読んだときに、聞く側と答える側のどちらも経験があるなーと思いました。そして、聞かれた際は、どんな答え方をしたらいいのか困ったのに、いざ自分が聞く側になったら、同じように聞いていることもあるなと、思い返しました。
●「なぜ」と聞きたくなったら「いつ?」と聞く
「なぜ、どうして」と聞きたくなったら、それを一度飲み込んで、「いつ」という事実質問に置き換えて質問すべし、というものです。
「なぜ質問」の場合、質問の対象となるのは、「意識を生きる」「宿敵を生きる」にすぎない。初対面の人と話すのが「苦手」など、行為や出来事や現象です。つまり、その背景や原因や動機を「なぜ」という質問によって聞き出そうとするものです。これは言いくるめや都合のいい解釈、根拠の乏しい思い込みを引き出す良くない質問でしたね。この時「なぜ質問」は禁句にしてはいけません。
質問対象とする行為や出来事が一度きりの場合は、「そこにいつ就職したの?」など、「それをしたのはいつか」「起こったのはいつか」というような、そのことが起こった日時を特定する「いつ質問」に変換します。
特に継続的な出来事や現象、あるいは繰り返し起こっていることについては、初めと終わりがありますから、「一番最初はいつ?」または「一番最近はいつ?」と聞きます。
「いつ?」と聞いた後は、「その前に?」「その前は?」と時系列で聞き続けるのが筋道です。「なぜ?」と聞くと考え始めてしまいますが、「いつ?」「その前は?」と聞き続けられたら、思い出そうとしますよね。このプロセスが、思い込みを排して、事実を確認していく行為となるわけです。
―――――――――――
この部分を読んだときに、自分が、「いつ」と聞かれていたら、事実しか頭に浮かばないなと思いました。使う場面はそれぞれだとは思いますが、思い込みを排除して、事実を知るうえで重要な言葉だと感じたのと同時に、シンプルで使いやすいので意識して使っていきたいです。
●「どう」と聞かずに「何」「いつ」「どこ」「誰」と聞く
「なぜ質問」の対象は行為や出来事や現象で、目的はその背景や原因や動機を知ることでした。「どう質問」は、「どう?」のひと言で考えなどを一気に聞いてしまおうという怠惰な質問です。聞かれたほうは「相手が何が知りたいのかはっきりわからない状態」のまま、何が思いついたことを答えようとします。二人の間には当然、モヤがかかります。
ここでの基本公式は、その出来事や現象を少しだけ分解して、何がいつ****どこで「誰に(誰と)起こったか、と聞くことです。
以下の「どう質問」は、どのように変えられますか。考えてみてください。
例)試合、どうだった?(野球の試合を終えた友人に対して)
相手との関係にもよりますが、こちらが聞きたいことは「試合の結果」と「友人のプレーの出来(活躍具合)」に絞り込めるはずです。
まず、試合の結果は秘密でも何でもないでしょうから、突然聞いてもいいでしょう。ただ唐突さを避けるために、「相手は〇〇チームでしたよね?」などと軽い確認の質問をまず行ってから、「で、結果は?」と聞くとより自然に話に入っていけます。
友人のプレーの出来についても同じです。「前の試合と同じように、サードを守ったの?」と聞いてから「何を打ったの?」「最後まで出たの?」などと聞き続ければ、相手は必ず「打撃はよかったんだけど、大事なところでエラーしてしまって...」などと自分から語り始めてくれるはずです。それをうけて、さらに聞いていけば、やがて相手から自発的に話をしてくれるという流れが自然にできていきます。そうなると、他の友人には話しにくいような微妙な話も出てくるかもしれません。
まどろっこしいように思えるかもしれませんが、このように、相手が答えやすい、事実質問から入っていくことで、状況を具体的に思い出してもらう環境を整えることができます。
正確に思い出して答えてもらえなければ、質問する意味がありません。
―――――――――――
この部分は、よく言ってしまうなーと率直に思いました。
教室での子どもたちに、「運動会はどうだった?」「今日はどうだった?」など、何気なく発してしまっていますが、このどう質問を置き換えると、「運動会は何組だったの?」「今日は朝何時に起きたの?」など、答えやすい質問にすることができるかなと思いました。
著書の中から私が共感した部分や実践したいと感じた内容を抜粋していきました。
思い込みではなく事実を思い出してもらう質問の方法や、答えやすい質問をすることで、相手が今どんなことを考えているのか、どんな気持ちなのかを知ることができると著書を通して知ることができました。
これらは著書の一部ですが、人と会話をする際には抜粋した部分を中心に思い出しながら、質問をしていきたいと思います。
有水愛佳
2026.02.02
『殻を破れば生まれ変わるかもしれない』
2026.01.07
『親子で育てる ことば力と思考力』
2026.01.06
『最高のコーチは、教えない。』
2026.01.05
『HIDDEN POTENTIAL 可能性の科学 あなたの限…
2025.12.28
『とりあえずやってみる技術』
2025.12.26
『ながーい5ふん みじかい5ふん』
2025.12.09
『Little Book of Choice Theory …
2025.12.02
『夢2.0 ~夢を再定義する~』
2024.12.31
『勝つ理由。<3人の金メダリストを育てた名将がひもとく勝利の…
2024.12.31
『このプリン、いま食べるか? ガマンするか? 一生役立つ時間…
2024.12.05
『ディズニー そうじの神様が教えてくれたこと』
2024.11.30
『ゆっくり変わる』
2023.12.30
子育てに必要な4つのこと
2023.12.01
『習慣が10割』
2023.12.01
『リーダーは話し方が9割』
2023.11.01
『選択の科学 コロンビア大学ビジネススクール特別講義』
2021.10.16
『運動の大切さ』
2021.10.16
『伸びる子どもは◯◯がすごい』
2021.10.01
「どうせ無理」と思っている君へ
2021.10.01
『本当の「頭のよさ」ってなんだろう?』
横浜本校

みなとみらい校

江古田校

金沢八景校

横浜本校(スイミング)








