スタッフブログ
2025.06.28
『アオアシに学ぶ「考える葦」の育ち方 カオスな環境に強い「頭のよさ」とは』
みなさん、こんにちは。齋藤です。
梅雨になり暗く湿っぽい空の日も増えましたが、小学校ではプール授業も始まり、日焼けした姿や、冷たい水の〝地獄のシャワー〟の話をする子どもたちのパワーでプール内では元気いっぱいにぎやかな毎日です。
さて今回、私が読んだ本は『アオアシに学ぶ「考える葦」の育ち方』です。
梅雨になり暗く湿っぽい空の日も増えましたが、小学校ではプール授業も始まり、日焼けした姿や、冷たい水の〝地獄のシャワー〟の話をする子どもたちのパワーでプール内では元気いっぱいにぎやかな毎日です。
さて今回、私が読んだ本は『アオアシに学ぶ「考える葦」の育ち方』です。
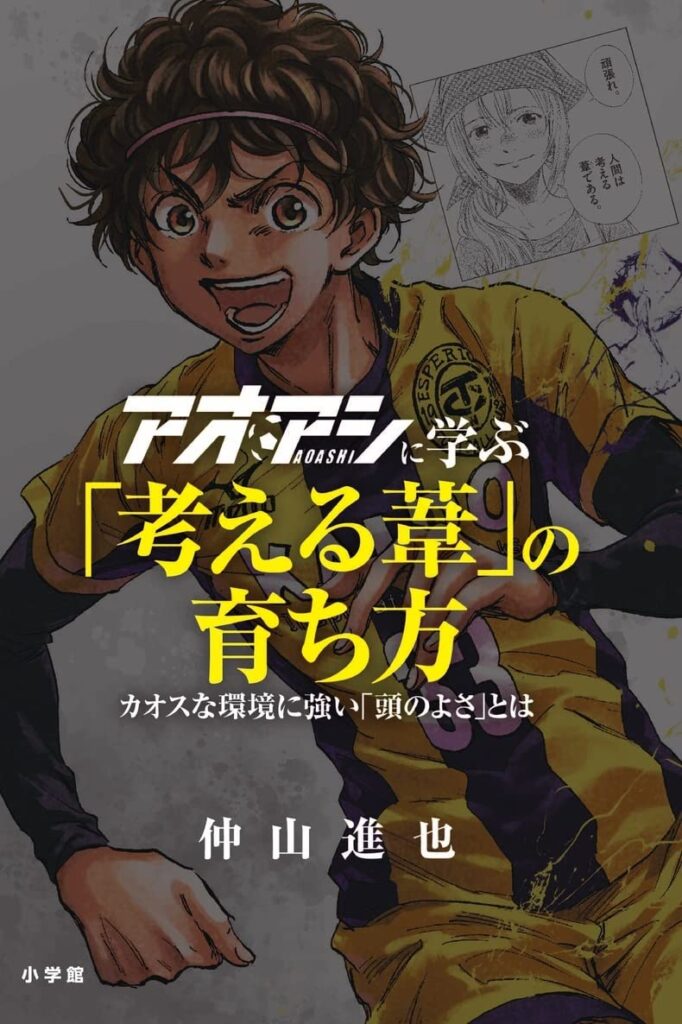
この本を読んだきっかけは、スポーツアニメを観て思いもよらず涙し、登場人物に共感し、観入ってしまいました。アニメの中に何かメッセージ性のようなものが含まれていて人を引き付ける秘密が隠されているのではないかと感じて読むことにしました。
「アオアシ」というマンガを簡単に説明すると、主人公の成長を描く人気のサッカー漫画で、サッカーをするのに必要な能力を持ちながらもユースチームで全く通用せず、周囲の助けを得ながら次第に才能を開花させていく過程が描かれています。
そしてマンガでは育成をテーマとして「思考力」を重視しているのが面白いところです。実際のユースチームも選手の成長をはかる際の基準が思考力のようです。自分で考え行動できる思考型人材を育成するヒントが書かれています。
あらゆるところで『自分で考え行動する人材に育てることが大事』だとよく聞きますが、「自分で考えて行動する」とは具体的に何をどうすることなのか。その仕組みを整理してみると「観察→判断→実行」というループになるというのが、本の結論の1つでした。このループを常に回すことが自立型人材を育てるポイント。
では、この「観察」「判断」「実行」3つのループをどのようにすればいいのか、本ではマンガのアオアシに出てくるシーンと照らし合わせながら解説しているのでサッカーを全く知らない私でも解りやすかったので少し紹介してみます。
◎観察
まず「観察」です。「観察」の次には「判断」がきますが、判断には「判断するための材料」が必要となりです。そこで大事になるのが、材料を仕入れるために観察です。本では観察をする際の重要点が以下のように紹介されていました。
* 視点⇒視線が注がれているところ。対象物の何、どこを見るか
* 視野⇒目に見えている広さ。どこまで見えて、見えている範囲のこと
* 視座⇒物事を見る姿勢や立場。どこから見るか、見ている位置
* 視差⇒観察位置によって同じ対象物の見え方が異なる現象。
『観察』=〝物事の状態や変化を注意深くみること〟と簡単に思っていたのですが、書かれている4点が一つでも違えば見えているものが違い、次に行う判断が全く違うものになってくることに気がつきます。
観察はただの情報インプット作業ではなく、良い判断を下すための最も重要な作業となるのではないでしょうか。
スイミングや体操の先生たちも生徒の様子やレッスン時の変化等は注視して観察をし、声を掛けています。しかしどの位置でどのような気持ちで観るかによって全く違ってくるならば、指導をしている時に多角的な関わりや先生たちが同じ思いを持って接することが大切だと感じました。
また本では情報をインプットする際のヒントもくれています
入力情報=情報量(どれくらい多くの情報に触れたか×吸収力(接した情報のうち、どれだけ吸収できたか)と表されています。良い情報のインプットを増やすには、視野を広げてたくさんの情報に触れることが必要ですが、ただ集めた情報を自分の中に吸収できなければ、たくさん集めても意味がありません。吸収力の高さも重要になるようですが吸収力とは・・・と思いませんか?
吸収力とは、情報を正確に深く理解をするということで、その人の持つ価値観や心理状況によって情報の理解や質量に変化を与えてしまうものです。吸収力も高くするために常に素直な気持ちで思い込みや偏見を持たず物事に接するよう意識することも大切だと知りました。
◎判断
次は「判断」についてです。「判断」を分解すると「価値基準×入力情報」になります。入力された情報を解釈し、思いついたいくつかの選択肢の中から、どれが一番いいかの評価をして選択をすることが「判断をする」ということです。
良い判断をするには良い価値基準を持つこと。ここで大事なのが「1.1の力」。
* 普通の状態を「1.0」
* 少しご機嫌・ポジティブ・やる気がある状態を「1.1」
* 少し不機嫌・ネガティブ・やる気がない状態を「0.9」
と表現します。「1.1」と「0.9」の人が一緒に仕事をすると、掛け算になるので1.1×0.9=0.99になり、「1.0」の状態よりも悪くなってしまいます。
よくポジティブな考えや言葉を使うと米田功スイミングスクールでも言い続けていますが、この計算式を見た時にハッと気がつきました。ポジティブの意味をこのように数字で表し、目で観える物に置き換えてみると一目瞭然。「1.0」以下の状態で判断をすると「1.0」以下の結果しか出せないのです。判断だけではなく存在自体も「1.1」の状態でいることが重要ではないか。私はどちらかというと「心配性」な方で物事を「0.9」で考えがちなタイプです。入力された情報を常に「1.1」で解釈し判断する意識をしていくよう練習が必要だと思いました。
◎実行
最後が「実行」です。
* 仮説を立てる:「理想」を設定する
* 試行をする :考えるために行動し、結果「現実」が確定する
* 検証 :振り返り、課題が見えてくる。課題=理想-現実
* 規範化する :学びを得る。価値基準と視点をアップデートする
この4点をサイクルでおこない計画やアイデアを形にして実現させたり、理想に近づけるために行動すること。
しかし実行するうえで5段階の壁を乗り越える必要があり
* 「知らない」を学んで「知る」に変える知識の壁
* 得た知識を実際に「やってみる」行動の壁
* 実際にやってみて「分かる」に変える気づきの壁
* 「分かる」から「できる」に変える技術の壁
* 「できる」を「している」に変える習慣の壁
つまり努力し続ける行動を反復し、考えなくても「できている」にすることを実行というのです。3日坊主になりがちな私としては耳が痛い内容でしたが明確な目的を持つことで実行のサイクルはできやすいとも書かれていました。実行のサイクルを続けるために理想をしっかり思い描き、常に振り返りをしていく必要性を感じました。
「観察・判断・実行」というのは、最後の「実行」で終わりではなく、振り返りながらこのループを回していくことが重要なのです。「観察から判断」「判断から実行」そして「実行から観察」と、それぞれのステップで必ずフィードバックがあるはずです。これを常に頭の中でグルグルと回すことが、思考が上がっていくことにつながるのです。
米田功スイミングスクールではレッスン後の「振り返り」を大切にしています。今回この本を読みながら最終的に振り返りが次の思考の元を生み出すことを再確認できました。生徒との関わりや指導内容を振り返り、整理をして、より良いレッスンを提供していきたいと思いました。
齋藤美紀
「アオアシ」というマンガを簡単に説明すると、主人公の成長を描く人気のサッカー漫画で、サッカーをするのに必要な能力を持ちながらもユースチームで全く通用せず、周囲の助けを得ながら次第に才能を開花させていく過程が描かれています。
そしてマンガでは育成をテーマとして「思考力」を重視しているのが面白いところです。実際のユースチームも選手の成長をはかる際の基準が思考力のようです。自分で考え行動できる思考型人材を育成するヒントが書かれています。
あらゆるところで『自分で考え行動する人材に育てることが大事』だとよく聞きますが、「自分で考えて行動する」とは具体的に何をどうすることなのか。その仕組みを整理してみると「観察→判断→実行」というループになるというのが、本の結論の1つでした。このループを常に回すことが自立型人材を育てるポイント。
では、この「観察」「判断」「実行」3つのループをどのようにすればいいのか、本ではマンガのアオアシに出てくるシーンと照らし合わせながら解説しているのでサッカーを全く知らない私でも解りやすかったので少し紹介してみます。
◎観察
まず「観察」です。「観察」の次には「判断」がきますが、判断には「判断するための材料」が必要となりです。そこで大事になるのが、材料を仕入れるために観察です。本では観察をする際の重要点が以下のように紹介されていました。
* 視点⇒視線が注がれているところ。対象物の何、どこを見るか
* 視野⇒目に見えている広さ。どこまで見えて、見えている範囲のこと
* 視座⇒物事を見る姿勢や立場。どこから見るか、見ている位置
* 視差⇒観察位置によって同じ対象物の見え方が異なる現象。
『観察』=〝物事の状態や変化を注意深くみること〟と簡単に思っていたのですが、書かれている4点が一つでも違えば見えているものが違い、次に行う判断が全く違うものになってくることに気がつきます。
観察はただの情報インプット作業ではなく、良い判断を下すための最も重要な作業となるのではないでしょうか。
スイミングや体操の先生たちも生徒の様子やレッスン時の変化等は注視して観察をし、声を掛けています。しかしどの位置でどのような気持ちで観るかによって全く違ってくるならば、指導をしている時に多角的な関わりや先生たちが同じ思いを持って接することが大切だと感じました。
また本では情報をインプットする際のヒントもくれています
入力情報=情報量(どれくらい多くの情報に触れたか×吸収力(接した情報のうち、どれだけ吸収できたか)と表されています。良い情報のインプットを増やすには、視野を広げてたくさんの情報に触れることが必要ですが、ただ集めた情報を自分の中に吸収できなければ、たくさん集めても意味がありません。吸収力の高さも重要になるようですが吸収力とは・・・と思いませんか?
吸収力とは、情報を正確に深く理解をするということで、その人の持つ価値観や心理状況によって情報の理解や質量に変化を与えてしまうものです。吸収力も高くするために常に素直な気持ちで思い込みや偏見を持たず物事に接するよう意識することも大切だと知りました。
◎判断
次は「判断」についてです。「判断」を分解すると「価値基準×入力情報」になります。入力された情報を解釈し、思いついたいくつかの選択肢の中から、どれが一番いいかの評価をして選択をすることが「判断をする」ということです。
良い判断をするには良い価値基準を持つこと。ここで大事なのが「1.1の力」。
* 普通の状態を「1.0」
* 少しご機嫌・ポジティブ・やる気がある状態を「1.1」
* 少し不機嫌・ネガティブ・やる気がない状態を「0.9」
と表現します。「1.1」と「0.9」の人が一緒に仕事をすると、掛け算になるので1.1×0.9=0.99になり、「1.0」の状態よりも悪くなってしまいます。
よくポジティブな考えや言葉を使うと米田功スイミングスクールでも言い続けていますが、この計算式を見た時にハッと気がつきました。ポジティブの意味をこのように数字で表し、目で観える物に置き換えてみると一目瞭然。「1.0」以下の状態で判断をすると「1.0」以下の結果しか出せないのです。判断だけではなく存在自体も「1.1」の状態でいることが重要ではないか。私はどちらかというと「心配性」な方で物事を「0.9」で考えがちなタイプです。入力された情報を常に「1.1」で解釈し判断する意識をしていくよう練習が必要だと思いました。
◎実行
最後が「実行」です。
* 仮説を立てる:「理想」を設定する
* 試行をする :考えるために行動し、結果「現実」が確定する
* 検証 :振り返り、課題が見えてくる。課題=理想-現実
* 規範化する :学びを得る。価値基準と視点をアップデートする
この4点をサイクルでおこない計画やアイデアを形にして実現させたり、理想に近づけるために行動すること。
しかし実行するうえで5段階の壁を乗り越える必要があり
* 「知らない」を学んで「知る」に変える知識の壁
* 得た知識を実際に「やってみる」行動の壁
* 実際にやってみて「分かる」に変える気づきの壁
* 「分かる」から「できる」に変える技術の壁
* 「できる」を「している」に変える習慣の壁
つまり努力し続ける行動を反復し、考えなくても「できている」にすることを実行というのです。3日坊主になりがちな私としては耳が痛い内容でしたが明確な目的を持つことで実行のサイクルはできやすいとも書かれていました。実行のサイクルを続けるために理想をしっかり思い描き、常に振り返りをしていく必要性を感じました。
「観察・判断・実行」というのは、最後の「実行」で終わりではなく、振り返りながらこのループを回していくことが重要なのです。「観察から判断」「判断から実行」そして「実行から観察」と、それぞれのステップで必ずフィードバックがあるはずです。これを常に頭の中でグルグルと回すことが、思考が上がっていくことにつながるのです。
米田功スイミングスクールではレッスン後の「振り返り」を大切にしています。今回この本を読みながら最終的に振り返りが次の思考の元を生み出すことを再確認できました。生徒との関わりや指導内容を振り返り、整理をして、より良いレッスンを提供していきたいと思いました。
齋藤美紀
2025.12.28
『とりあえずやってみる技術』
2025.12.26
『ながーい5ふん みじかい5ふん』
2025.12.09
『Little Book of Choice Theory …
2025.12.02
『夢2.0 ~夢を再定義する~』
2024.12.31
『勝つ理由。<3人の金メダリストを育てた名将がひもとく勝利の…
2024.12.31
『このプリン、いま食べるか? ガマンするか? 一生役立つ時間…
2024.12.05
『ディズニー そうじの神様が教えてくれたこと』
2024.11.30
『ゆっくり変わる』
2023.12.30
子育てに必要な4つのこと
2023.12.01
『習慣が10割』
2023.12.01
『リーダーは話し方が9割』
2023.11.01
『選択の科学 コロンビア大学ビジネススクール特別講義』
2021.10.16
『運動の大切さ』
2021.10.16
『伸びる子どもは◯◯がすごい』
2021.10.01
「どうせ無理」と思っている君へ
2021.10.01
『本当の「頭のよさ」ってなんだろう?』
横浜本校

みなとみらい校

江古田校

金沢八景校

横浜本校(スイミング)








