スタッフブログ
2025.08.10
『センスは知識からはじまる』
こんにちは、小川です。
いよいよ夏本番!今年の夏も、しっかりと暑さ対策をして乗り切りましょう。
今回は、グッドデザインカンパニー代表・水野学さんの著書『センスは知識からはじまる』を読ませていただきました。水野さんは、クリエイティブディレクター/クリエイティブコンサルタントとして、相鉄グループ、熊本県のくまモン、三井不動産のロゴ、東京ミッドタウン、再春館製薬のドモホルンリンクルなど、数々のデザインを手がけてきた方です。
いよいよ夏本番!今年の夏も、しっかりと暑さ対策をして乗り切りましょう。
今回は、グッドデザインカンパニー代表・水野学さんの著書『センスは知識からはじまる』を読ませていただきました。水野さんは、クリエイティブディレクター/クリエイティブコンサルタントとして、相鉄グループ、熊本県のくまモン、三井不動産のロゴ、東京ミッドタウン、再春館製薬のドモホルンリンクルなど、数々のデザインを手がけてきた方です。
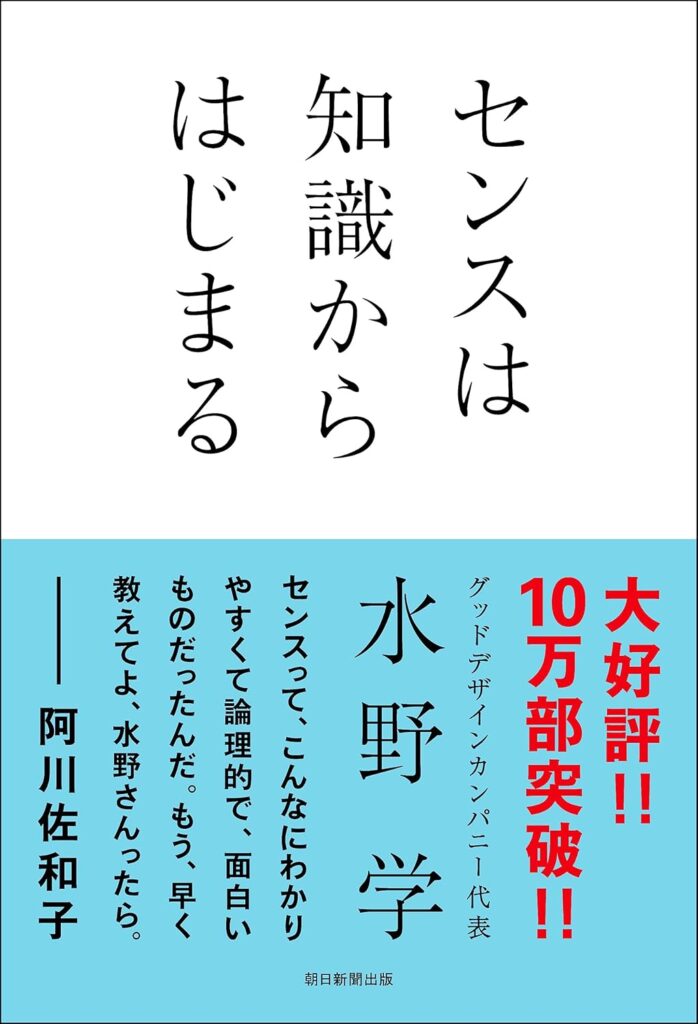
私たちの日常において「センス」と聞くと、ファッションセンスが良い、インテリアのセンスがあるといったことが思い浮かぶかもしれません。スポーツの世界でも、動きにセンスがある、フォームがきれい、バランス感覚が良い、判断力が高いなど、さまざまな形で「センス」が語られます。
私はこれまで、センスとは教えられるものではなく、それぞれが生まれつき持っている感性だと考えていました。しかしこの本の中で、「センスとは生まれつきのものではない」と明言されており、とても興味深く感じました。では、センスとは何なのか。本の中で特に共感した部分を、いくつか紹介したいと思います。
■センスとは知識の集積である
センスがいい文章を書くには、言葉をたくさん知っていたほうが圧倒的に有利である。これは仕事や生きるということにおいても同様だと思います。知識があればあるだけ、その可能性を広げることができるのです。知識というのは紙のようなもので、センスとは絵のようなものです。紙が大きければ大きいほど、そこに描かれる絵は自由でおおらかなものになる可能性が高くなっていきます。
→以前から、生まれ持った才能だけではスポーツの世界で一流にはなれないと感じていました。才能に努力を重ねることで成長し、さらにそこに「センス=知識」が加わることで、才能が開花するのだと強く共感しました。「知識の幅が広がれば、可能性もさらに広がる」どんな絵を描くのか?知識を集積し、この言葉をこれからも常に意識していきたいと思います。
■センスとは知識にもとづく予測である
よきセンスをもつには、知識を蓄え学ぶことが大切です。同時にセンスとは、時代の一歩先を読む能力も指します。過去を知って知識を蓄えること、未来を読んで予測することは、一見すると矛盾しているように感じます。しかしこの二つは明確につながっています。
→知識には、現在だけでなく「過去」にもヒントがあると感じました。トップ選手たちの考え方や行動、練習への取り組み方は、どの時代でも学ぶべき点がたくさんあります。
過去の知識を学び考えながら、今後発展していく技術の進化や採点基準、常に時代の流れを予測し、準備を進めていくことが大切だと再認識しました。
■客観情報の集積がその人のセンスを決定する
センスをよくするためには、単に流行りの情報を収集するだけではいけません。数値化できない事象を最適化するためには、客観情報ほど大切なものはありません。センスの最大の敵は思い込みであり、主観性です。思い込みと主観による情報をいくら集めても、センスは良くならないのです。思い込みを捨てて客観情報を集めることこそ、センスをよくする大切な方法です。
→体操においても同じことが言えると思いました。自分が知っている技術、考えている技術ではなかなか成果が出ないときには、一度、客観的に見直す必要があります。考える幅を持つことだと思います。答えは一つではなく、無限にある。そうした前提に立ち、特定のやり方に固執しすぎないように意識していきたいと思います。
本の中では、「センスとは、特別な人に備わった才能ではない」と繰り返し語られています。センスを高めるためには、まず知識を増やすこと、そして視野を広げることが重要です。
選手と関わる時も「センス」の捉え方を間違えないように、個々が本当の意味でセンスを磨けるように知識を学ぶきっかけを作っていきたいと感じました。
そして、選手たちの可能性を広げていくために私自身もさらにセンスを高め、指導の現場に活かしていきたいと考えています。
小川泰弘
私はこれまで、センスとは教えられるものではなく、それぞれが生まれつき持っている感性だと考えていました。しかしこの本の中で、「センスとは生まれつきのものではない」と明言されており、とても興味深く感じました。では、センスとは何なのか。本の中で特に共感した部分を、いくつか紹介したいと思います。
■センスとは知識の集積である
センスがいい文章を書くには、言葉をたくさん知っていたほうが圧倒的に有利である。これは仕事や生きるということにおいても同様だと思います。知識があればあるだけ、その可能性を広げることができるのです。知識というのは紙のようなもので、センスとは絵のようなものです。紙が大きければ大きいほど、そこに描かれる絵は自由でおおらかなものになる可能性が高くなっていきます。
→以前から、生まれ持った才能だけではスポーツの世界で一流にはなれないと感じていました。才能に努力を重ねることで成長し、さらにそこに「センス=知識」が加わることで、才能が開花するのだと強く共感しました。「知識の幅が広がれば、可能性もさらに広がる」どんな絵を描くのか?知識を集積し、この言葉をこれからも常に意識していきたいと思います。
■センスとは知識にもとづく予測である
よきセンスをもつには、知識を蓄え学ぶことが大切です。同時にセンスとは、時代の一歩先を読む能力も指します。過去を知って知識を蓄えること、未来を読んで予測することは、一見すると矛盾しているように感じます。しかしこの二つは明確につながっています。
→知識には、現在だけでなく「過去」にもヒントがあると感じました。トップ選手たちの考え方や行動、練習への取り組み方は、どの時代でも学ぶべき点がたくさんあります。
過去の知識を学び考えながら、今後発展していく技術の進化や採点基準、常に時代の流れを予測し、準備を進めていくことが大切だと再認識しました。
■客観情報の集積がその人のセンスを決定する
センスをよくするためには、単に流行りの情報を収集するだけではいけません。数値化できない事象を最適化するためには、客観情報ほど大切なものはありません。センスの最大の敵は思い込みであり、主観性です。思い込みと主観による情報をいくら集めても、センスは良くならないのです。思い込みを捨てて客観情報を集めることこそ、センスをよくする大切な方法です。
→体操においても同じことが言えると思いました。自分が知っている技術、考えている技術ではなかなか成果が出ないときには、一度、客観的に見直す必要があります。考える幅を持つことだと思います。答えは一つではなく、無限にある。そうした前提に立ち、特定のやり方に固執しすぎないように意識していきたいと思います。
本の中では、「センスとは、特別な人に備わった才能ではない」と繰り返し語られています。センスを高めるためには、まず知識を増やすこと、そして視野を広げることが重要です。
選手と関わる時も「センス」の捉え方を間違えないように、個々が本当の意味でセンスを磨けるように知識を学ぶきっかけを作っていきたいと感じました。
そして、選手たちの可能性を広げていくために私自身もさらにセンスを高め、指導の現場に活かしていきたいと考えています。
小川泰弘
2026.02.02
『殻を破れば生まれ変わるかもしれない』
2026.01.07
『親子で育てる ことば力と思考力』
2026.01.06
『最高のコーチは、教えない。』
2026.01.05
『HIDDEN POTENTIAL 可能性の科学 あなたの限…
2025.12.28
『とりあえずやってみる技術』
2025.12.26
『ながーい5ふん みじかい5ふん』
2025.12.09
『Little Book of Choice Theory …
2025.12.02
『夢2.0 ~夢を再定義する~』
2024.12.31
『勝つ理由。<3人の金メダリストを育てた名将がひもとく勝利の…
2024.12.31
『このプリン、いま食べるか? ガマンするか? 一生役立つ時間…
2024.12.05
『ディズニー そうじの神様が教えてくれたこと』
2024.11.30
『ゆっくり変わる』
2023.12.30
子育てに必要な4つのこと
2023.12.01
『習慣が10割』
2023.12.01
『リーダーは話し方が9割』
2023.11.01
『選択の科学 コロンビア大学ビジネススクール特別講義』
2021.10.16
『運動の大切さ』
2021.10.16
『伸びる子どもは◯◯がすごい』
2021.10.01
「どうせ無理」と思っている君へ
2021.10.01
『本当の「頭のよさ」ってなんだろう?』
横浜本校

みなとみらい校

江古田校

金沢八景校

横浜本校(スイミング)








