スタッフブログ
2025.09.01
『知的複眼思考法 誰でも持っている創造力のスイッチ』
こんにちは!あゆむ先生です!
今年の夏は去年よりも暑い…!と毎年言っているほど年々暑さが増してきいてますねー… 水分補給だけでなく定期的に涼しい部屋で休むなど体調管理をしっかりして今年の夏も乗り越えましょう!
さて、今回私がご紹介させていただく本は『知的複眼思考法 誰でも持っている創造力のスイッチ』という本です。
「知的複眼思考法」とは、ありきたりの常識や紋切り型の考え方にとらわれずに、ものごとを考えていく方法というように本文で書かれていました。 つまり、「〇〇はこうだ!」というような1つの視点から捉え思考を止める(単眼思考)のではなく、自らの視点からものごとを捉え「なぜ〇〇はこうなのか」と自分の頭で考え抜くということです。
今年の夏は去年よりも暑い…!と毎年言っているほど年々暑さが増してきいてますねー… 水分補給だけでなく定期的に涼しい部屋で休むなど体調管理をしっかりして今年の夏も乗り越えましょう!
さて、今回私がご紹介させていただく本は『知的複眼思考法 誰でも持っている創造力のスイッチ』という本です。
「知的複眼思考法」とは、ありきたりの常識や紋切り型の考え方にとらわれずに、ものごとを考えていく方法というように本文で書かれていました。 つまり、「〇〇はこうだ!」というような1つの視点から捉え思考を止める(単眼思考)のではなく、自らの視点からものごとを捉え「なぜ〇〇はこうなのか」と自分の頭で考え抜くということです。
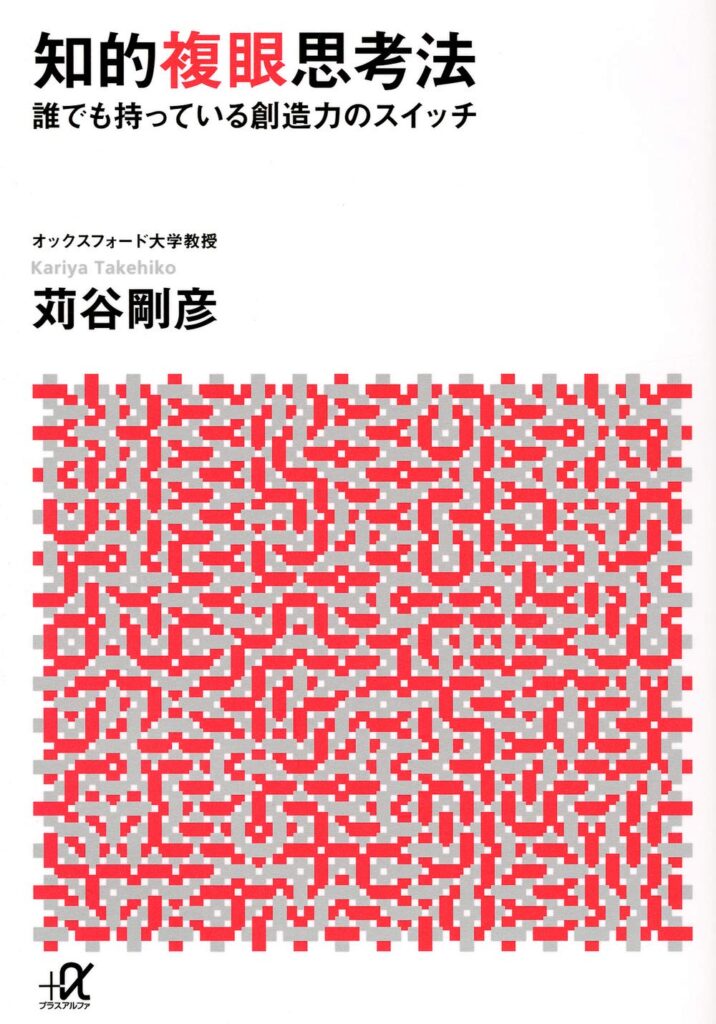
この思考法を知り、私自身教室の中で、「子どもが泣いている→嫌なことがあった」「子どもが笑っている→嬉しいことがあった」というように「〇〇だからこうだ」という思考で止まり「なにが嫌だったのか」「なぜ嬉しかったのか」までの考えに行き着くことが少ないなと改めて感じました。
ではどうすればこの複眼思考が身につくのか。 本文の中から「なるほど…!」と感じた点を3つ抜粋してご紹介します!
○「正解」がどこかにあるという発想から抜け出す。 「唯一の正解というひとつの視点→ものごとには多様な側面がある、見る視点によってその多様な側面が違って見える。」
これは体操教室の練習の中でも大いに当てはまることだなと感じました。
例えば、その日上手くいった練習が次の週に同じことをやったらあまり上手くいかなかったというようなパターンがありました。 この時に「この練習は上手くいかないから正解の練習を探そう」という考え方ではなく、①先週と今週で子どもの様子はどうだったか(少し疲れていた、先週の方が楽しそうにしていた、来た時から元気だった、あまり元気がなかった) ②体育館の気温はどうだったか(先週より暑かった、寒かった、晴れていた、雨が降っていた) ③子どもに対する声かけはどうだったか (子どものやる気を引き出すような声かけはあったか、子どもに伝わりやすい言葉で伝えられていたか) というように練習内容という視点だけではなく多様な視点から見ることで、この練習は正解だった、不正解だったという1つの視点から抜け出すことができます。 そして、これら複数の視点から考察した時に「子どもに伝わりやすい声かけをしよう」「練習前に子どもとのコミュニケーションを増やしてみよう」というように1つの視点からでは見えてこなかった点を見つけ改善していけば、再度同じ練習をした場合、一番最初よりも良い練習になると思います!
○要はどう読むか 「何かを知ろうと思って読むのか、それとも自分なりに考えて読むのか。」
これは、ただ知識として頭に入れるだけで終わりにするのではなく、その知識を自分ならどう活かすかを考えて頭に入れるということです!
今ではSNSなどで様々な体操の技術練習や遊びを交えた面白そうな運動プログラムをよく目にします。 自分もこれらの内容を参考にすることがありますが、ただ知識として頭に入れて同じようにやるのではなく、「米田功体操クラブの特徴や魅力を最大限に活かしながらやるにはどうしたら良いか」と考えながらプログラムに組み込むことが重要だと考えています。 米田功体操クラブでは「あいさつをする」「人の話を聞く」「夢を宣言する」など大切にしている10個のテーマがあります! (教室内にも貼ってあるのでぜひご覧くださ い!) これらのテーマやカラフルな器具を組み合わせて、このクラブの魅力を子どもたちだけではなく保護者の方たちにも伝わるような教室を展開していきます!
〇『疑問』と『問い』の違い
『疑問』は「変だなぁ」「不思議だなぁ」など感じて終わるものに対して、『問い』は立てるもので、答える行為を前提にしている。また、答えを探し出そうとする行動につながっていく。 というように本文で説明されています。
例えば、体操教室で子どもが「これがやりたい!」「これができるようになりたい!」というように自分の意思を伝えてきてくれた時に、ただその言葉を聞いて「そうなんだ」と感じて終わりにしてしまうと子どもへの言葉がけが「がんばろう」や「やってみよう」など抽象的もので終わってしまいます。もし、具体的にどうすれば良いのか知りたい子がこの返答をされたら「せっかく先生に話したのに欲しい答えが返ってこなかったな…」というように受け取られてしまうかもしれません。また、自分の話を聞いてほしい子だった場合も「なんか適当な返事だな…」と受け取られてしまうかもしれません。ですがそこで「なぜ自分に伝えてくれたのか」「この子はどうしてこれをしたいのか」まで考えることによって「いいね!まずは〇〇の練習からやってみよう!」や「これが上手になると伝えてくれた技もできるようになるから毎回の教室で〇回は練習しよう!」など具体的な言葉がけができるようになっていきます! そうなれば「あ、ちゃんと考えてくれた!」というように受け取ってもらえて、そこで1つ信頼関係が築いていけると思います!
少し極端な話になってしまったかもしれませんが、やはり「疑問」で終わらせずに「問い」に変え、子どもたちのことを考えて言葉にする、行動することが大切だと思います!
以上3つのポイントを抜粋してご紹介しましたが、これらをまとめてみて、簡単に答えを出すのではなく最後まで思考を止めずに考え抜くことが重要だと感じました。 また、複数の視点からものごとを見ることで得られた新たな気づきやヒラメキが根本の問題だけでなく別の問題解決のヒントにつながっていくので、小さなことでも自分の中で「問い」を立て考えを深めていこうと思います!
これからも子どもたちや保護者の皆様にとってより良い教室にしていけるよう思考を止めず、全力を尽くしていきますので、引き続きよろしくお願いいたします!
あゆむ先生
ではどうすればこの複眼思考が身につくのか。 本文の中から「なるほど…!」と感じた点を3つ抜粋してご紹介します!
○「正解」がどこかにあるという発想から抜け出す。 「唯一の正解というひとつの視点→ものごとには多様な側面がある、見る視点によってその多様な側面が違って見える。」
これは体操教室の練習の中でも大いに当てはまることだなと感じました。
例えば、その日上手くいった練習が次の週に同じことをやったらあまり上手くいかなかったというようなパターンがありました。 この時に「この練習は上手くいかないから正解の練習を探そう」という考え方ではなく、①先週と今週で子どもの様子はどうだったか(少し疲れていた、先週の方が楽しそうにしていた、来た時から元気だった、あまり元気がなかった) ②体育館の気温はどうだったか(先週より暑かった、寒かった、晴れていた、雨が降っていた) ③子どもに対する声かけはどうだったか (子どものやる気を引き出すような声かけはあったか、子どもに伝わりやすい言葉で伝えられていたか) というように練習内容という視点だけではなく多様な視点から見ることで、この練習は正解だった、不正解だったという1つの視点から抜け出すことができます。 そして、これら複数の視点から考察した時に「子どもに伝わりやすい声かけをしよう」「練習前に子どもとのコミュニケーションを増やしてみよう」というように1つの視点からでは見えてこなかった点を見つけ改善していけば、再度同じ練習をした場合、一番最初よりも良い練習になると思います!
○要はどう読むか 「何かを知ろうと思って読むのか、それとも自分なりに考えて読むのか。」
これは、ただ知識として頭に入れるだけで終わりにするのではなく、その知識を自分ならどう活かすかを考えて頭に入れるということです!
今ではSNSなどで様々な体操の技術練習や遊びを交えた面白そうな運動プログラムをよく目にします。 自分もこれらの内容を参考にすることがありますが、ただ知識として頭に入れて同じようにやるのではなく、「米田功体操クラブの特徴や魅力を最大限に活かしながらやるにはどうしたら良いか」と考えながらプログラムに組み込むことが重要だと考えています。 米田功体操クラブでは「あいさつをする」「人の話を聞く」「夢を宣言する」など大切にしている10個のテーマがあります! (教室内にも貼ってあるのでぜひご覧くださ い!) これらのテーマやカラフルな器具を組み合わせて、このクラブの魅力を子どもたちだけではなく保護者の方たちにも伝わるような教室を展開していきます!
〇『疑問』と『問い』の違い
『疑問』は「変だなぁ」「不思議だなぁ」など感じて終わるものに対して、『問い』は立てるもので、答える行為を前提にしている。また、答えを探し出そうとする行動につながっていく。 というように本文で説明されています。
例えば、体操教室で子どもが「これがやりたい!」「これができるようになりたい!」というように自分の意思を伝えてきてくれた時に、ただその言葉を聞いて「そうなんだ」と感じて終わりにしてしまうと子どもへの言葉がけが「がんばろう」や「やってみよう」など抽象的もので終わってしまいます。もし、具体的にどうすれば良いのか知りたい子がこの返答をされたら「せっかく先生に話したのに欲しい答えが返ってこなかったな…」というように受け取られてしまうかもしれません。また、自分の話を聞いてほしい子だった場合も「なんか適当な返事だな…」と受け取られてしまうかもしれません。ですがそこで「なぜ自分に伝えてくれたのか」「この子はどうしてこれをしたいのか」まで考えることによって「いいね!まずは〇〇の練習からやってみよう!」や「これが上手になると伝えてくれた技もできるようになるから毎回の教室で〇回は練習しよう!」など具体的な言葉がけができるようになっていきます! そうなれば「あ、ちゃんと考えてくれた!」というように受け取ってもらえて、そこで1つ信頼関係が築いていけると思います!
少し極端な話になってしまったかもしれませんが、やはり「疑問」で終わらせずに「問い」に変え、子どもたちのことを考えて言葉にする、行動することが大切だと思います!
以上3つのポイントを抜粋してご紹介しましたが、これらをまとめてみて、簡単に答えを出すのではなく最後まで思考を止めずに考え抜くことが重要だと感じました。 また、複数の視点からものごとを見ることで得られた新たな気づきやヒラメキが根本の問題だけでなく別の問題解決のヒントにつながっていくので、小さなことでも自分の中で「問い」を立て考えを深めていこうと思います!
これからも子どもたちや保護者の皆様にとってより良い教室にしていけるよう思考を止めず、全力を尽くしていきますので、引き続きよろしくお願いいたします!
あゆむ先生
2025.12.28
『とりあえずやってみる技術』
2025.12.26
『ながーい5ふん みじかい5ふん』
2025.12.09
『Little Book of Choice Theory …
2025.12.02
『夢2.0 ~夢を再定義する~』
2024.12.31
『勝つ理由。<3人の金メダリストを育てた名将がひもとく勝利の…
2024.12.31
『このプリン、いま食べるか? ガマンするか? 一生役立つ時間…
2024.12.05
『ディズニー そうじの神様が教えてくれたこと』
2024.11.30
『ゆっくり変わる』
2023.12.30
子育てに必要な4つのこと
2023.12.01
『習慣が10割』
2023.12.01
『リーダーは話し方が9割』
2023.11.01
『選択の科学 コロンビア大学ビジネススクール特別講義』
2021.10.16
『運動の大切さ』
2021.10.16
『伸びる子どもは◯◯がすごい』
2021.10.01
「どうせ無理」と思っている君へ
2021.10.01
『本当の「頭のよさ」ってなんだろう?』
横浜本校

みなとみらい校

江古田校

金沢八景校

横浜本校(スイミング)








